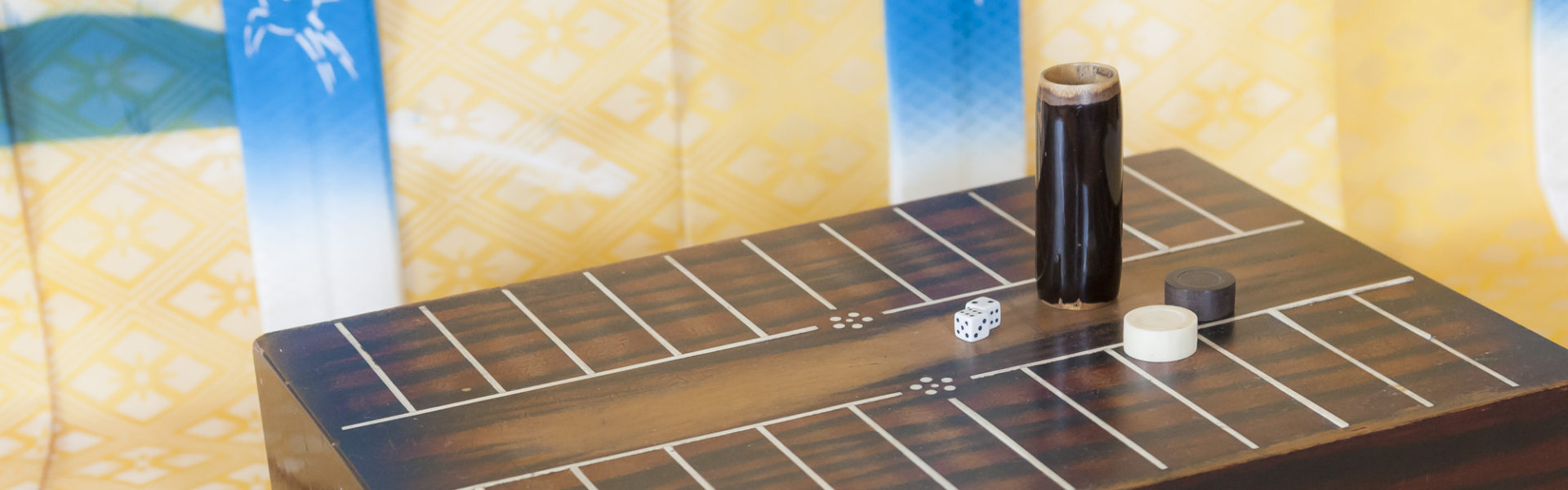今様は言うまでもなく歌謡ですが、ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞するくらいですから、今様にももちろん詩としての文芸的価値が認められます。
詩の形式は、韻律によって成り立っています。
〈韻〉=音色
〈律〉=リズム
今様について言えば、代表的な〈律〉は、75757575という七五調のリズムです。
では、〈韻〉は?
と思ったときに、そもそも〈韻〉についての知識が自分にないことに気づき、基本知識を(てっとりばやく)仕入れねばと、九鬼周造『日本詩の押韻』を手に取りました。
九鬼周造は、明治生まれの哲学者です(脚注)。主著は『偶然性の問題』。なぜ哲学者の彼が押韻について研究したのかといえば、ある語とある語で韻を踏めるのは、それらの語が意味に関わりなくたまたま同じ音色を持つからであり、それは〈偶然性〉の具現に他ならない…からだそうです。果たしてほんとうにそうかと考えたくなりますが、それでは話がそれてしまうので、ここはとりあえず面白い人だなと思うに留め、先へ進みます。
日本語の音は、たいてい五十音で認識されるので、「韻を踏む」といってもこの五十の音の組合せしかないように思えますが、一音が子音と母音から成り立っていると意識すると、もう少し多くのパターンを数えることができるようです。
たとえば、〈よいこyoiko〉と〈まいこmaiko〉ではikoが共通しているのは明解ですが、ここへ〈せいろseiro〉や〈せびろsebiro〉をもってきても、末尾のiとoが共通しており脚韻を踏んでいるとみなすこともできます。もちろん強弱の差はあります。
一般に日本の詩歌では、脚韻よりも頭韻のほうがよく使われるようです。頭韻では子音の役割が大きく、わかりやすくいえば、カ行ならカ行、サ行ならサ行で始まる語を並べるだけでも効果があるということです。
名こそ流れてなほ聞こえけれ na-na-na ナ音
花が開いてほっとした ha-hi-ho ハ行
〈頭韻〉〈脚韻〉の他に、〈掛詞〉(注1)や〈枕詞〉(注2)もまた押韻の一種だと氏は説きます。〈同語反復〉は偶然性にたよらない必然的な押韻。助詞・助動詞を無視した句末で韻を踏む〈散韻法〉、さらに、音ではなく〈視覚的な韻〉(注3)もあると。
注1:九鬼氏によると、同音異義語を一語にまとめてしまう〈掛詞〉は、究極の押韻。まさに「止揚された韻」
〈松matsu〉と〈待つmatsu〉で韻を踏むべきところ→〈まつ〉一語に重ねる。
注2:意味よりも音のつながりによるものが多い。
つがの木のいやつぎつぎの
注3:奈良七重七堂伽藍八重桜(芭蕉)
このようにさまざまな韻の形を列挙されると、もしかするとわたしたちは特に意識しなくとも、これくらいの韻は自然に踏んでいるのではないかと気づきます。規則によってではなく、なんとなく調べがよいと思って選んだ語が、九鬼氏的に分析するなら、何らかの韻を踏んでいるということになるのです。
ですから韻を踏むのは、そう難しいことではない。むしろ、踏みすぎて駄洒落と堕さないこと、また押韻の効果を疎外するような音や言葉を周囲に置かないことなどの配慮が大切だと言えます。
そのことについて、短歌の場合ですが、押韻の失敗例を〈歌病〉として綴った『歌経標式』が紹介されています。奈良時代、藤原浜成によって記された歌学書です。
内容については漢詩論の引き写しで日本の詩には当てはまらないという評価もあるようですが、当時から日本の歌壇に押韻という概念のあったことの証左であり、実作指南としてなかなか示唆に富んでいるように思えます。
〈腰尾の病〉〈頭尾の病〉〈胸尾の病〉〈黶子の病〉…など押韻効果を疎外する7つの例が挙げられています。一読するのもよろしいかもしれません。
今様の押韻例については項をあらためます。
***
注)九鬼周造は、明治生まれの哲学者で、大学卒業後ヨーロッパ諸国へ留学中、ドイツではリッケルトやハイデッガーに師事し、フランスではベルクソンと知己を得、フランス語はサルトルから習ったという経歴の持ち主。帰国後京都帝大に勤めたときには西田幾多郎も同僚だったそうですから、きっとともに〈哲学の道〉もそぞろ歩いたことでしょう。主著は『偶然性の問題』。長い外国暮らしの間に気づいた日本の美意識について『「いき」の構造』も著しました。
父は高級官僚。周造を懐妊中の母波津子が、夫を捨てて岡倉天心のもとへ走ったという逸話はかなり有名です。
犬君書